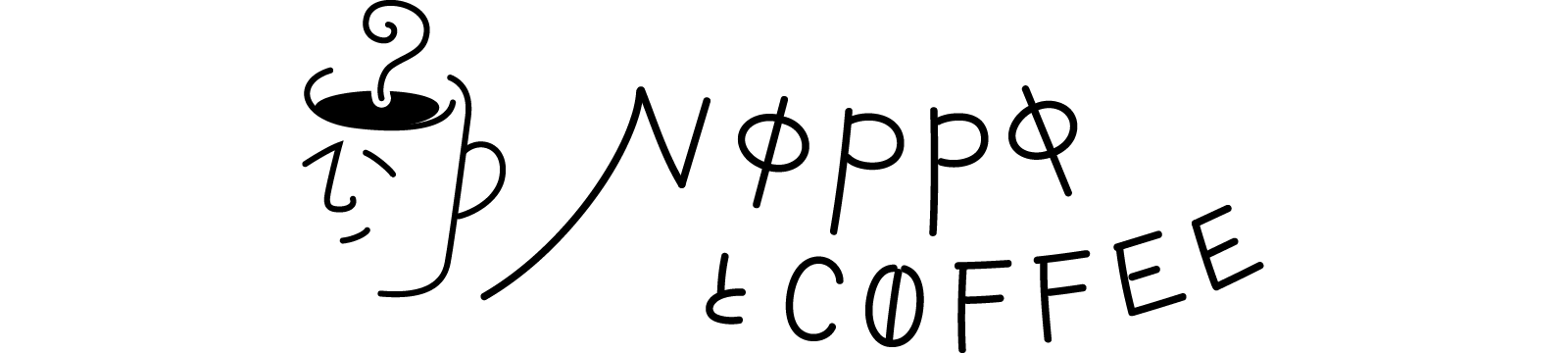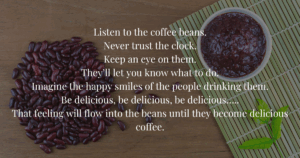『カムカムエヴリバディ』の“あんこのおまじない”は、コーヒーにも効くのか?
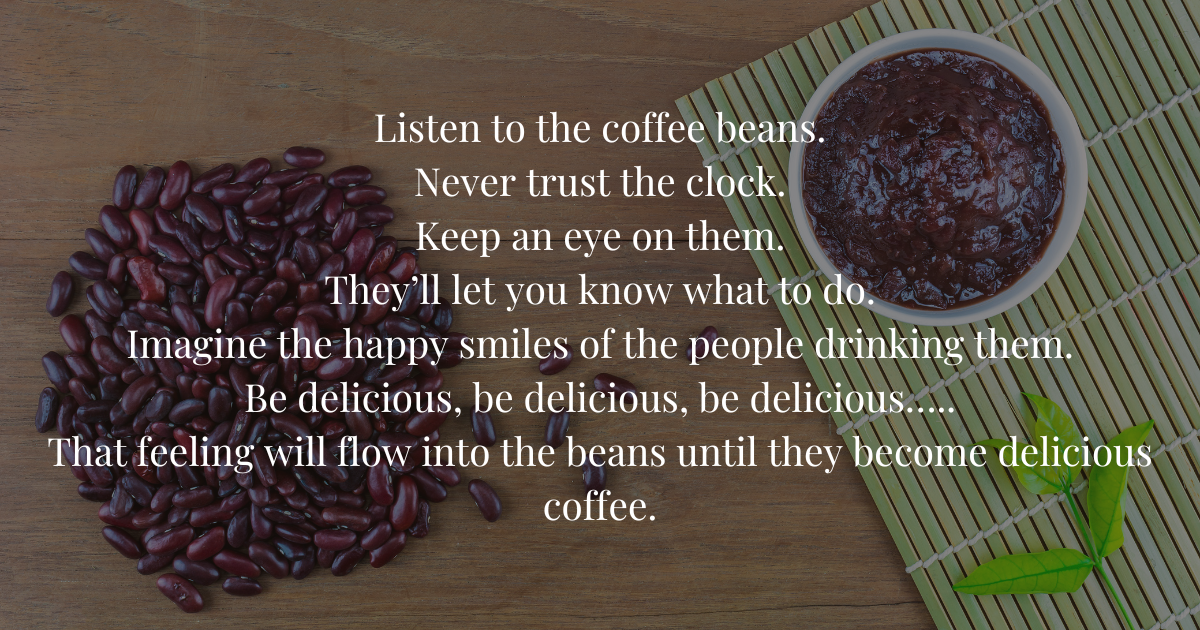
いま、NHK朝ドラ『カムカムエヴリバディ』が再放送されていて、初見なのにどっぷりハマってしまっている人たちが続出している。
かくいう私もそのひとり。あの世界観、あの言葉たちの一つひとつが、なぜこんなに沁みるのだろう。
その中でも特に心に残ったのが、“あんこのおまじない”。
小豆を炊くときに唱えられる、まるで呪文のようなことばだ。
「小豆の声を聴け
時計に頼るな
目を離すな
何をしてほしいか小豆が教えてくれる
食べる人の幸せそうな顔を思い浮かべぇ
おいしゅうなれ
おいしゅうなれ
おいしゅうなれ
その気持ちが小豆に乗り移る
うんとおいしゅうなってくれる
甘ぇあんこが出来上がる」
この「おまじない」が登場するのは、物語の前半、ヒロイン・安子(やすこ)が家業の和菓子屋で、小豆と真剣に向き合う場面。
これはただの言い伝えや演出ではなく、数字では測れない「おいしさ」に向き合うための、知恵のかたまりなのだ。
そして、この考え方はまるで鏡のように、コーヒーの焙煎や抽出の世界にも映し出されている。
数字か感覚か。「おいしゅうなれ」だけで美味しくなるのか?
なぜ私たちは、数字でも温度でもなく、「ことば」や「気持ち」に頼ろうとするのか?
そして逆に、なぜ私たちは「感覚」に頼らず、「正確さ」や「科学」によって味を再現しようとするのか?
それは、コーヒーの世界にも通底する問いだ。
焙煎の度合い、抽出の温度、粉の量。それらを数字で完全にコントロールしようとするバリスタの世界においても、最後に問われるのは「うまいかどうか」、ただそれだけである。
では、数字を超える“おまじない”は、本当に必要なのか?
あるいは、数字を信じることは、感覚を捨てることになるのか?
小豆やコーヒー豆の声を聴く
コーヒーの世界では、「味」は数値で管理される。
焙煎温度、時間、豆の水分値、抽出比率、粉の粒度、TDS、pH…。
すべてがミリ単位で設計され、安定した品質のためにデータが積み上げられていく。
でも、本当に「うまい」と感じる一杯が生まれるのは、数字の先にある“感覚の領域”だ。
小豆を炊くときの「時計に頼るな」は、コーヒー焙煎にも通じる。
ロースターは、豆のはぜる音、香りの立ち方、色味の変化といった“数字で拾いきれない変化”を頼りに、火からおろすタイミングを決めている。
「小豆の声を聴け」——これはコーヒー豆にも言える。
抽出でも、粉の膨らみや抽出スピード、香り立ちの微妙な変化を「見て」「嗅いで」「感じて」調整する。
だからこそこのおまじないは、「数字では気づけない変化に気づくためのことば」として、とても本質的なのだ。
感覚と数値は対立しない。“重ねる”ものだ。
でも勘違いしてはいけない。
「時計に頼るな」「感覚を信じろ」という言葉は、数字なんていらない、という意味ではない。
むしろ逆だ。
感覚を最大限に働かせるには、まず正確な数字を知っていなければいけない。
なぜなら、感覚は「経験の蓄積」でできているからだ。
コーヒーの焙煎士も、抽出職人も、何百回、何千回とデータをとってきたからこそ、数字の外側にある「今、この豆に必要な一手」を感じとれる。
数字を知らなければ、感覚は育たない。
でも、数字だけでは、感覚に届かない。
その“あいだ”に立っているのが、「おまじない」なのだ。
それはレシピではなく、「どう向き合うか」を自分に問い直すためのことば。
気持ちが入ることで、作業が「祈り」に変わる。
数字で届かないところへ、気持ちで触れるということ
コーヒーを淹れるとき、豆を焙煎するとき、あるいは料理をするとき、私たちはたしかにタイマーを使い、温度計を見て、グラム単位で測っている。
でも最後の最後に、「おいしゅうなれ」と心の中でつぶやいてみたらどうだろう。
それは、自分の感覚を信じるということ。
そしてその感覚の中には、これまで培ってきたデータも、技術も、誰かの笑顔も、全部詰まっている。
数字でコントロールするだけでは届かない“おいしさ”に、気持ちで触れるために、人はことばを使う。
だからこのおまじないは、今の時代にこそ必要なのだ。