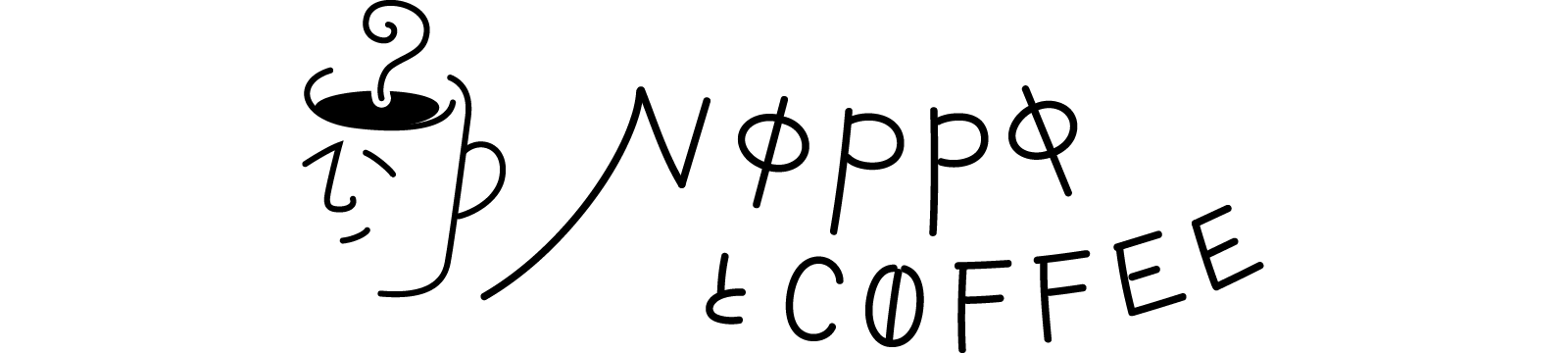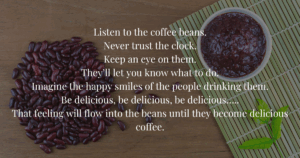【コーヒーコラム】なぜ人間は「苦み」を美味しく感じられるようになるのか?

私は小学生の娘にたまに「コーヒー飲んでみるか?」と勧めている。
娘は私がドリップしたコーヒー(ブラック)をおそるおそる一口飲んでみるのだが、「うわっ!にがっ!」と言い、申し訳なさそうに顔をしかめるのだ。
思い返すと、私自身も子どもの頃、ブラックコーヒーを口に入れたとき、娘同様顔をしかめた記憶がある。
しかし、いつのまにかコーヒーの”苦み”をむしろ「美味しい!」と感じられるようになっていた。
コーヒーの他にも、ホイコーローのピーマンやサンマの内臓なんかもそうだ。あの苦みがないとなにか物足りなさを感じる。
なぜ子どものころは苦手だった苦みを、大人になったら好きと思えるようになったんだろう?
これはただの「味覚の成長」だけの話ではない。
もしかしたら、”苦さ”がわかるようになるということは、“生き方”の変化と関係しているのではないだろうか?
あんなにイヤだったのに、なんで好きになったんだろう?
”苦いものは美味しくない”。私も人並みにそう思っていた。
だが、むしろ「この苦さがたまらない」と感じる瞬間が訪れた。
21歳の真夏、バンド仲間と行ったバーベキューで、燃えるような太陽の下で飲んだビール(ハイネケン)が、びっくりするほど美味しく感じたのである。
それまではビールが苦手だったのに、その一杯だけは、なんだか体にスッと染みわたって、「悪魔的にうまい…!」と自然に言葉が出た。
苦いはずなのに、苦くない。むしろその“苦さ”が気持ちよかった。
それ以来、「苦いって、もしかして“まずい”だけじゃないかも?」って思うようになった。
苦さは感覚的な「罰」から精神的な「報酬」へと変わる
”苦い”は本来、「危険」のシグナルだ。
人間の体は、最初から“苦いもの=危ない”と思うようにできているである。
毒を避けるために、子どもの味覚は本能的に「うわ、これムリ!」と感じるように設計されているらしい。
しかし大人になるにつれ、このセンサーは精度を変えていく。
私たちは、苦味=危険ではなく、苦味=複雑・奥深い・余韻、と再解釈しはじめるのだ。
なぜそんな変化が起こるのか?
- 味覚の慣れ
繰り返し食べたり飲んだりしてるうちに、「これは安全な苦さなんだ」と、味の受け止め方が変わってくる。 - “大人っぽさ”へのあこがれ
コーヒーをブラックで飲んでる人とか、苦いビールを楽しんでる人って、なんかちょっとカッコよく見える。そういうイメージから、苦味に対する感じ方が変わってくる。 - “すぐに気持ちよくならないもの”が、逆におもしろくなる
大人になると「苦しみを乗り越えた先にある快楽」が報酬として感じられるようになる。
コーヒー、お酒、激辛料理、薬膳…。「簡単じゃないもの」を楽しめるようになるのだ。
つまり苦味は感覚的な“罰”から、精神的な“報酬”に変化していくのだ。まるで人間そのものの成長過程をなぞるように。
苦味とは、”人生”そのものかもしれない
苦みとは、人生そのものではないだろうか?
甘さは簡単だ。与えられるもの。快楽の直行便。だが苦さには、「時間」と「理解」が必要だ。
苦味がわかるようになるとは、苦しみや矛盾を、まるごと抱えたまま愛する力が育ってきたということではないだろうか。
音楽、アート、哲学──深く味わえば味わうほど、そこには“苦味”が含まれている。
でも、だからこそ感動する。だからこそ、忘れられない。
そしてそれは、「成長したから受け入れられるようになった」のではない。
むしろ、「受け入れられるようになったとき、はじめて“本当の意味で成長した”と言える」のかもしれない。
私たちは、なぜ“苦いもの”を好きになるのか?
苦味は、“すぐにはわからない価値”の象徴だと思う。
理解されるまでに時間がかかる、だが一度その奥にある“美味しさ”を知ったとき、人はもう後戻りできないだろう。
この問いは、味覚の話にとどまらない。
「簡単じゃないもの」を、あなたはどう扱っているだろうか?
“苦い”と感じるものにこそ、人生の大事な核心が宿っているのではないだろうか?
子どものころは避けていた苦さを、今、舌の奥でじっくり味わっている自分に気づいたとき、私たちはただ年齢を重ねただけではなく、“深さ”を知る人間になったのだと、静かに誇ってもいいのではないだろうか。